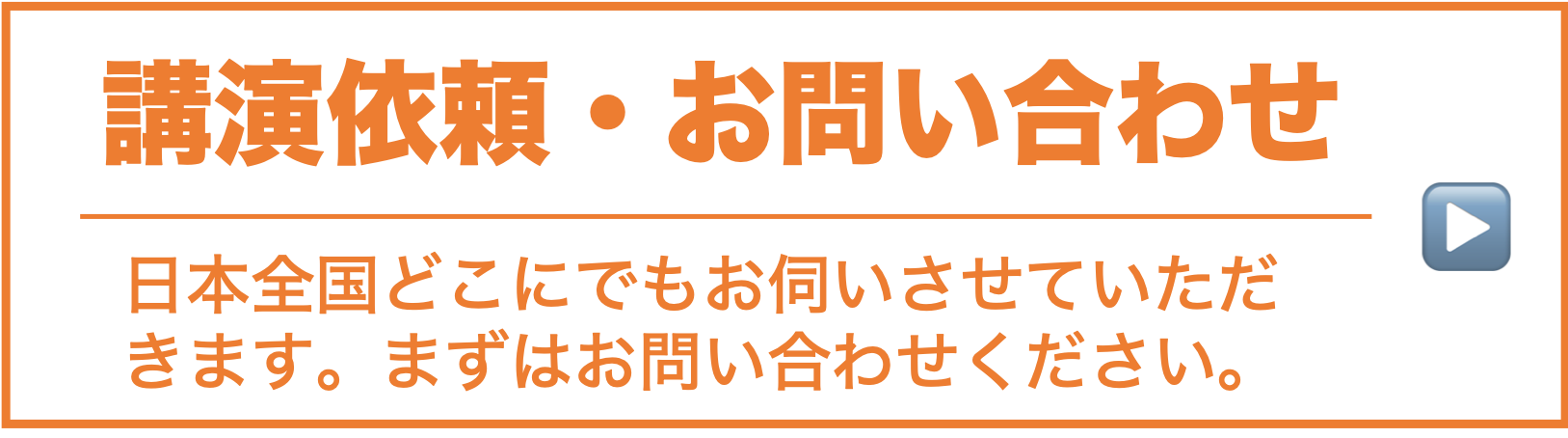ジャイロ総合コンサルティングの渋谷雄大です。
今日は2018年最後の日ですね。
大晦日みなさまはいかがお過ごしでしょうか。
わたしは休みに入ってからは仕事&大掃除を並行しながら続けて大晦日まで持ち越しです。
なんとか夜までには終わらせたい。
2019年に向けて色々と考えを巡らせています。
どうぞ2019年もよろしくお願いいたします。
6:4くらいがちょうど良い
年末は仕事の合間に、色々と本を読み漁っています。
昨日はツイッターで紹介されていた、柴田陽子さんのコンセプトライフという本を読んでみました。
読み終わった🍅
わたしの価値観とは60%くらい違うからこそ、興味深く読めたトマト🍅
共感できるところではなくって、共感できないところを見つけて、違いを楽しむのが好きトマト🍅
好きも好きだし、合わないのも楽しい🍅
だから本とか人とか選り好みしないトマト🍅
ありがとう🍅 https://t.co/A6VggoG83T
— たけひろ🍅少しだけおもしろいちょっとトマトの社長 (@kukkin999) December 30, 2018
正直いうと、こういうタイプの本はほとんど読まないのですが、信頼できる方がオススメしていた本なので早速読んでみました。
結論としては、良かったです。
良かったというのは、共感できた部分が4割。共感できなかったのが6割だったから。
100%共感できる本というのはとっても危ない。
だって、世間に合わせて書かれた可能性が高いという点が大きい。ヒットさせようとして書かれた本の多くは、概ね共感できる内容が多いです。
書き手のテクニックで概ね満足させる本は書けます。
でもこの本は、6割共感できなかったという点で、正直に書かれている本なのかなという印象です。
本を読むときは、半分以上が共感できないような本を選ぶことが基準。
だから本を選ぶときは、できる限り、普段行かないようなコーナーに向かいます。あとは人から薦められた本を買う。
その方が4:6の本に当たりやすいです。
共感できない部分が見極められるかどうかって自分自身の軸を持っているかどうかの基準になります。
好きな作家や経営者の本でも、理解できない部分や反対意見などをしっかり持つようにしています。
でないと、その筆者のたんなる信者になってしまうから。
筆者の信者になるための本を読むのではなく、自分自身の価値観を広げるために読書をする。
価値観の合わない本を選ぶ
そしてもうひとつ重視しているのが「価値観の合わない本」を選ぶようにしているということです。
「一流の人は、本のどこに線を引いているのか」という本に書かれていたと思います。
共感できる本では成長できない。
自分の価値観を後追いしているだけで、たんなる自己満足に過ぎない。
って書いてあったと。
そこから価値観の合わない本を選ぶようになりました。
今読んでいるのは、デカルトの方法序説(難しすぎる)。韓非子(ひとをしんようしない)という考え方真逆の本です。

非常に難しいし、今の時代に合わないところもあるかもしれませんが、その分学びも大きい。
人との付き合い方も同じです。
価値観が同じ人たちと付き合うのは、楽しいし、気持ちいいし、居心地も良いです。
でもそれは自分の幅や価値観を固定させることにも繋がりやすい。
価値観が同じ人と付き合う以上に、そうでない人の意見や付き合いをしていくことで、自分自身の殻を破っていかないといけない。
脱社畜っていう言葉が、流行っているけれど、それって脱社畜という価値観をもつ人たちで集まって気持ちは良いし、安心できるし、不安は解消できるかもしれないけれど、ほかの価値観を排除していることにも繋がってしまう。
会社に勤めること。
会社に勤めないこと。
そこに上下はなくって、それぞれの性格やライフスタイルに合わせて柔軟に変えれば良いだけのこと。
そのくらい社畜だろうが、脱社畜だろうが、まったく関係ないし、そもそもそこを論点にする必要が全くない。
どこかの意見に傾倒しすぎると、見えるものが見えなくなる。
わたしは社畜も脱もどっちも良し悪しがあるし、そもそもどっちを選ぶかなんて今まで考えたことがなかったので、逆に、なぜそこまで流行るのか?を学んでいるところです。