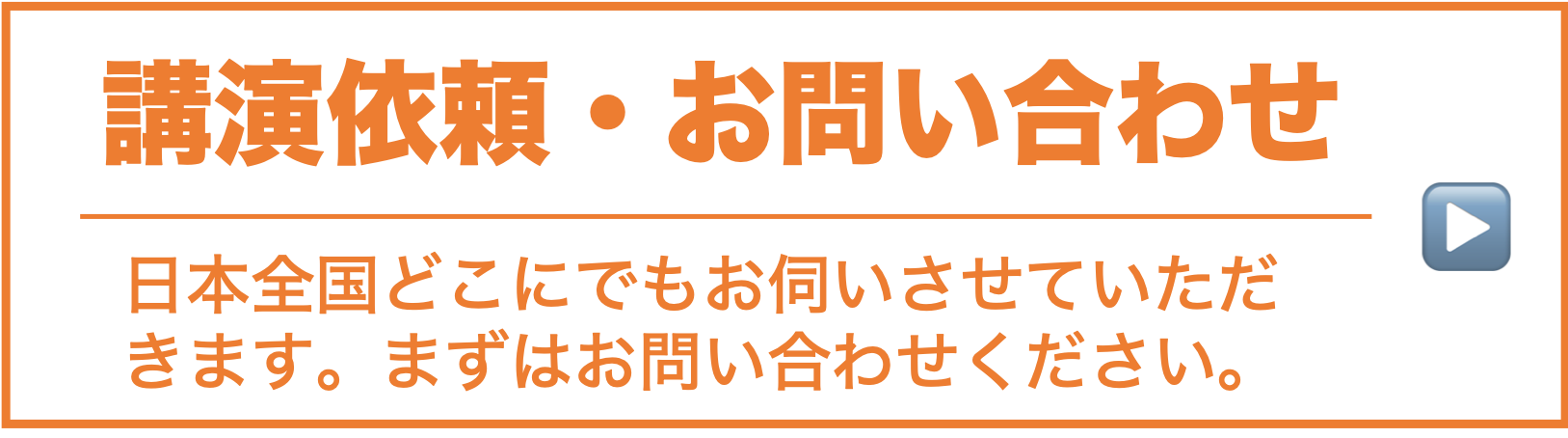ジャイロ総合コンサルティングの渋谷雄大です。
朝から猫に癒されておりました。

昨日は多摩ビジネスサポートセンター主催(八王子商工会議所)で事業承継セミナーをさせていただきました。

20名近くの方にお集まりいただき、事業を継ぐ側の具体的なポイントについてお話させていただきました。
そもそも承継と相続が混在しているのが問題
ユダヤの商人や華僑などビジネスの達人と呼ばれる人たちは、相続ではなく承継を重視しています。
日本では相続の話ばかりがセミナーで行われます。たしかに株の問題や資産相続などの手続き面は大切なことではあります。
でも相続=事業承継と捉えられているのも事実。承継と相続が混在されている傾向にあります。
承継とは、経営者の経営ノウハウなど目に見えない、先代から受け継がれるルールを継ぐことです。
相続とは、資産や株、従業員、取引先、顧客など目に見える資産を受け継ぐことです。
商売の達人である彼らが重きをおくのは、経営のルールの承継であり、極端なことを言えば、相続は最低限。
理由は簡単ですね。
相続で受け継いだ資産がどれほど膨大なものであったとしても、経営の勘所やルールが承継できていなければあっという間に枯渇し事業は行き詰まってしまうからです。逆に、相続は最低限であっても経営ノウハウやルールをしっかり承継できていればたとえ受け継いだ資産が少なかったとしても経営手腕で伸ばすことは可能です。
事業承継で考えるべきは、先代経営者が培ってきた経営感覚をいかにして後継者に引き継がせるか?という一点です。
逆に手続き面に関しては、法律家や専門家に任せることが一番確実なんです。
経営者の経営感覚を後継者に引き継がせるための具体策
では具体的にどうやって経営者の経営感覚を後継者に引き継いでいくのでしょうか?
時間はかかりますが簡単です。
現経営者の歴史を後継者に伝えることです。
経営者が何歳のときに、どうやって会社を立ち上げたのか?
その時の苦労や経験、岐路に立たされたときにどんな選択肢があって、どんな理由で決断したのか?
資金繰りが厳しくなった時、どうやって乗り越えてきたのか?
それは経営者が何歳のときに、どんな状況で起こったのか?
従業員のトラブルなどはあったのか?そのときにどんな説得をしていったのか?
後継者が知っている会社(経営者)の歴史はほんの一部であることが多いです。
後継者が知らない歴史をできる限り文書化して、話し合いながら共有化することが第一歩です。
ひとつひとつの歴史ととの時々の経営判断。経営判断の歴史こそが、事業承継における最重要ポイントなんです。
経営者にとって最大の仕事は、経営判断=決断です。
右に行くか?左に行くか?を最終的に決められるのは経営者だけです。
この決断によって事業が伸びるか?事業を停滞させるのか?が決まってきますね。
そして事業を拡大してきた経営者であれば、この決断能力が高かったと言えるわけです。
その決断能力を受け継ぐことができれば、どんな事業であっても伸ばすことができるわけです。
はじめから経営者の決断力が高かったわけではありません。創業社長であれば、たくさんの失敗を乗り越えながら決断力を磨いてきたんです。
おそらく、現経営者は感覚的に決断してきたため、うろ覚えかも知れません。しかし経営を継がせる総決算として、自分自身がどのような決断を行ってきたのか?を文書化してまとめることで、今後その企業が事業承継する場面で引き継がれていくんです。
家訓のようなものでしょうか。
松下幸之助などの経営者は、このような判断を文書にし、経営ルールの引き継ぎをしていますし書籍化もされていますね。
経営判断に関しては、時代の変化にはほぼ影響を受けません。
ある程度の真理が働くためバイブルとして活用できるものです。
残念ながら、ほとんどの経営者はこの決断力の承継をしないまま相続だけで終わる傾向が強いんです。
まずは過去の歴史とその都度の経営判断を事細かに後継者に伝えてみてください。その中から経営判断が磨かれていくんです。
また後継者はぜひ行ってほしいことがあります。
それはその次の後継者のために「経営日記」を書いてください。日々の決断を記録として残し、将来起こりうる次の事業承継のための準備をしておいて欲しいんです。
経営者は未来を予測して、準備しておくことです。だとしたらこの承継の仕組みは後継者はいまからやっておくことが使命です。
事業承継セミナー(継ぐ側の心構え)は全国で実施可能です。
ご興味ある主催者はお気軽にご連絡くださいね。